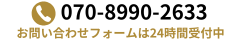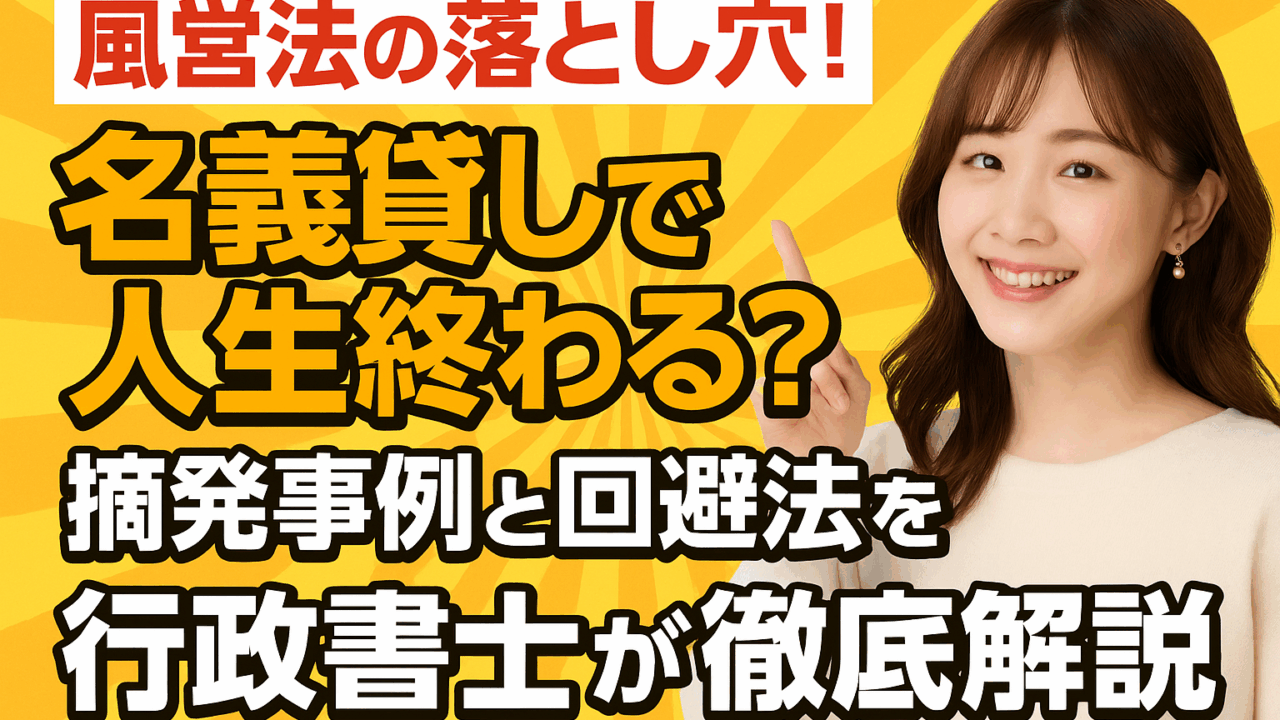はじめに
風営法に基づいて営業を行う際、「名義貸し」は絶対に避けるべき重大な違反行為です。許可を取得した名義人とは異なる人物が実際に経営を行っている場合、それは風営法第3条違反となり、許可の取消や刑事罰の対象になります。
名義貸しは「バレなければ大丈夫」と考え安易にされる方が多いですが、警察による立入調査や通報などで発覚すれば、即営業停止・逮捕に至るケースも珍しくありません。
名義貸しとは?
名義貸しとは、風営法の営業許可を取得した本人(名義人)とは異なる人物が、実際の経営を行っている状態を指します。
たとえば、Aさんが名義だけで許可を取り、実際の店舗運営はBさんがしているといったケースです。風営法では、営業許可を出す際に名義人の経歴や適格性を厳しく審査していますが、実際に営業している人物が別人であれば、その審査自体が無意味になってしまいます。
このような名義貸しは、制度の趣旨を根本から破壊する重大な法令違反とされ、行政処分や刑事罰の対象になります。表向きだけ整えても、実態がともなっていなければリスクは高まる一方です。
風営法の健全な運用のためにも、名義と実態が一致した経営が求められます。
なぜ名義貸しが問題なのか?
1.誰が責任者かわからない
営業中にトラブルが起きたとき、警察も行政も「誰が責任者なのか」を明確に把握している必要があります。しかし名義貸しをしていると、「名前だけ貸してる人」と「実際に指示を出している人」が別になるため、責任の所在が不明瞭になってしまいます。
2.警察のチェックがすり抜けられる
営業許可を取るには、名義人の素性を細かく審査されます。過去の違反歴や暴力団との関係などもチェックされるのですが、実際の経営者が別人だとその審査の意味がなくなってしまいます。つまり、リスクのある人物が裏で営業できてしまうのです。
3.違法営業の温床に
名義貸しが横行している店舗は、実際には法令無視の経営が行われているケースも多くあります。結果として、風俗営業全体へのイメージ低下にもつながってしまいます。
名義貸しに関する罰則とリスク
風営法における名義貸しは、単なるルール違反では済まされません。発覚すれば、行政処分だけでなく刑事罰の対象となる重大な違反行為です。
許可取消・営業停止の可能性
風営法第12条では、「他人に名義を使用させた場合」、公安委員会は営業許可を取り消すことができると明記されています。さらに、違反の程度や悪質性に応じて営業停止命令が出されるケースもあります。
つまり、一度でも名義貸しが発覚すれば、店舗の営業継続は非常に難しくなり、事業そのものの存続が危ぶまれる事態となります。
刑事罰のリスク
名義貸しは、実質的には無許可営業と見なされます。
そのため、風営法第3条違反に該当し、名義人だけでなく実際の経営者も処罰の対象となります。科される刑罰は以下の通りです
- 2年以下の懲役または200万円以下の罰金(風営法第52条)
- 法人が関与していた場合は、両罰規定により法人自体も処罰対象に
実際に摘発された事例では、名義貸しを行ったことで実刑判決が下されたケースも少なくありません。
周囲への波及も深刻
名義を貸した人物だけでなく、それを知っていながら関与したとされる行政書士・ビルオーナー・物件仲介業者なども警察から事情聴取を受ける可能性があります。
地域全体の風営関連事業者への目が厳しくなり、結果として合法に営業している店舗にまで悪影響が及ぶケースもあります。
名義貸しは、事業者本人だけでなく関係者すべてにリスクがあるという点を、決して軽視してはなりません。
実際にあった名義貸しの摘発事例
名義貸しは理論上のリスクにとどまらず、実際に多くの店舗で摘発され、営業停止・逮捕・実刑判決といった重い結果を招いています。ここでは、実際に警察によって摘発された名義貸しの実例を紹介します。
事例1:東京都新宿区・歌舞伎町の風俗店(2019年)
営業許可の名義人は表向き一般人でしたが、実際に経営を取り仕切っていたのは暴力団関係者でした。警察が内偵捜査を進める中で、金の流れや経営指示の記録から名義貸しが発覚。店舗は即日営業停止となり、名義人および実質経営者の両名が逮捕され、後に実刑判決が下されました。
この事例は、名義を貸す行為が反社会的勢力の隠れ蓑として悪用されるリスクを強く示しています。
事例2:大阪市中央区・ガールズバー(2022年)
表面上は女性名義で風俗営業許可を取得していましたが、裏で実際の運営を行っていたのは別の男性でした。しかもその男性には過去に風営法違反の前歴があり、許可を取得することができない人物でした。
警察が立入調査を行った際、営業資料や接客マニュアルに男性の名前や筆跡が複数確認され、名義貸しが明らかに。
許可は取り消され、店舗は営業停止となりました。
事例3:福岡市・無店舗型デリヘル(2021年)
法人名義で営業していたデリヘル業者が、実際には許可を受けていない元従業員によって運営されていたケースです。警察の立入検査により、複数の従業員が「実質的な経営者は別にいる」と証言。
さらに、運営指示のLINE履歴などから名義貸しの実態が裏付けられました。
結果として法人全体が行政処分を受け、同系列の他事業にも影響が波及しました。
注意点
これらの事例は、名義貸しが単なる形式的違反ではなく、風営法に基づく許可制度を根底から崩す重大な行為であることを物語っています。
どの事例でも、名義人と実質経営者が共に処罰され、店舗運営が継続不可能になっています。風営法の適正運用を守るためにも、名義と経営の実態が一致しているかを常に意識することが必要です。
名義貸しを防ぐために大切なこと
名義貸しによる風営法違反を避けるには、日々の営業実態と許可名義人の関係性を明確に保つことが重要です。
許可を取っただけで現場にはノータッチという状態は、警察から「実質経営者が別にいるのでは?」と疑われる大きな要因になります。
営業実態と名義人の一致
名義人本人が経営の中核に関わっていることが、最も基本的かつ重要なポイントです。帳簿管理や従業員のシフト作成、備品の発注、売上報告など、具体的な業務にどこまで携わっているかが、名義貸しと判断されるかどうかの分かれ目になります。
営業所に常駐しているか?
名義人が実際に営業所に出入りしているか、または常駐しているかもチェックされる要素です。立入調査の際、名義人が現場に不在で、従業員がその存在を把握していないようであれば、「名義だけ貸しているのでは?」と判断される恐れがあります。
専門家への相談が最も確実
「家族で経営する場合は?」「共同出資だが名義は1人」など、複雑な事情があるケースも少なくありません。そういった場合は、必ず風営法に精通した行政書士へ相談しましょう。事前に適法な経営体制を整えることで、無意識のうちに名義貸しに該当してしまうリスクを回避できます。
まとめ
名義貸しは、単なる形式的な違反ではなく、風営法における重大な法令違反です。発覚すれば営業許可の取消、営業停止、さらには刑事罰の対象にもなり、店舗の継続は極めて困難になります。
また、名義を貸した側だけでなく、関与した周囲の関係者にも悪影響が及ぶリスクがあります。風営法の世界では「知らなかった」では通用しません。