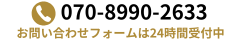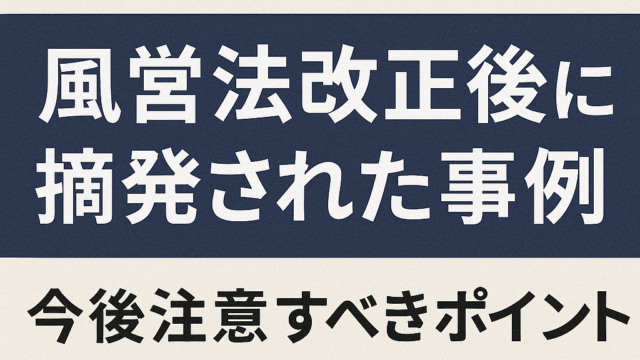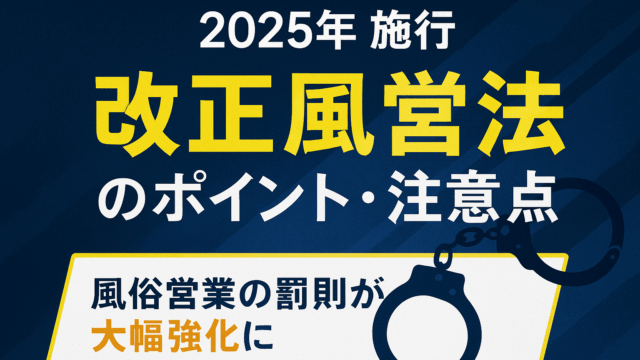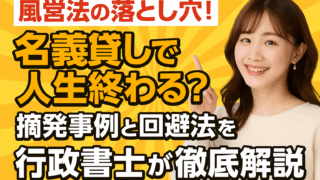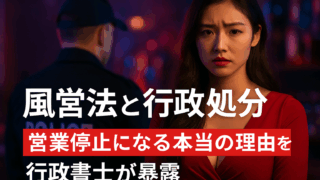はじめに
「スナックやバーを開業したいけど、深夜まで営業できるのか不安…」
「風営法の許可って必要?それとも“深夜酒類提供飲食店営業”の届出だけで大丈夫なの?」こうした疑問を抱える方は、ナイトビジネスを始める多くの事業者に共通する悩みです。
特に、ガールズバーやラウンジのように接客を伴う業態では、「どの法律に基づく手続きを行うべきか」という判断を誤ると、営業停止や罰則といった重大なリスクにつながりかねません。風営法許可と深夜酒類提供営業は一見似ていますが、法律上の区分や営業可能な時間、接待行為の有無など、実はまったく異なる規制が適用されます。
風営法許可とは?その目的と対象営業
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)とは、接待や遊興を伴う営業に対して、社会秩序の維持や青少年保護、善良な風俗の保持を目的として制定された法律です。この法律に該当する「風俗営業」を行うには、公安委員会の許可が必要となり、厳格な規制を受けることになります。
風俗営業に該当する主な業種(第2条第1項)は以下のとおりです
- キャバクラ(1号営業):接待・お酒・歓談を伴う業態
- ダンスホール、ディスコ(1号営業):客にダンスをさせる施設
- スナック(カラオケ設備+接待あり):飲食とともに接待を行う小規模店舗
- ガールズバー(接待行為があれば):見た目はバーでも実態が接待ありの場合
これらの業態では、たとえば次のような制限が設けられています:
- 深夜0時以降の営業禁止(原則)
- 保全対象施設(学校・保育園など)から100m以上の距離確保
- 店舗構造の制限(照度、客室の間取り、見通しなど)
風営法許可に該当するかどうかの判断を誤ると、無許可営業で摘発される可能性もあるため、開業前にしっかりと確認しておくことが重要です。
深夜酒類提供飲食店営業とは?
「深夜酒類提供飲食店営業」とは、午前0時以降に主として酒類を提供する飲食店で、接待行為を行わない業態を対象とする営業形態です。
風俗営業とは異なり、許可制ではなく届出制となっており、営業開始前に所轄の警察署へ「営業開始届出書」を提出することが義務付けられています。
この制度の対象となる主な店舗は以下の通りです:
- バー
- パブ
- スナック(接待なし)
この営業形態は「風俗営業」には該当しないため、深夜0時以降の営業も可能です。
ただし、接待行為が1つでもあれば風俗営業とみなされ、届出だけでは違法営業となります。また、店舗の所在地が用途地域等の関係で深夜営業自体が認められていないケースもあり、事前の調査が不可欠です。
深夜酒類提供飲食店営業は、風営法の適用を一部受ける形となっており、立入調査や行政指導の対象となる場合もあります。
誤った認識で営業を始めると、営業停止や是正命令を受けるリスクがあるため、制度の正確な理解が必要です。
両者の違いを徹底比較
| 項目 | 風俗営業(例:キャバクラ) | 深夜酒類提供飲食店(例:バー) |
| 法的区分 | 許可制(風営法第2条) | 届出制(風営法第33条の2) |
| 接待行為 | あり | なし(あれば違反) |
| 営業時間 | 原則24時まで | 深夜(24時以降)も可能 |
| 許可要件 | 厳格(人的・構造的・場所的) | 比較的緩やか |
| 対象例 | キャバクラ、ガールズバー(接待あり) | バー、パブ、ガールズバー(接待なし) |
| 距離制限 | あり(保全施設100m以上) | なし |
よくある誤解とそのリスク
風営法や深夜酒類提供飲食店営業に関しては、開業前の段階で誤解してしまいやすいポイントが多く、実際に違法営業や行政処分へと発展する事例も少なくありません。
以下に、特に多い3つの誤解を紹介し、それぞれのリスクを解説します。
誤解①:「ガールズバーだから深夜営業OKでしょ?」
ガールズバーであっても、女性スタッフがカウンター越しにお酌したり、会話をリードしたり、カラオケの相手をするなどの接待行為があれば風俗営業に該当し、深夜営業は違法となります。見た目が「バー」でも、実態が「接待あり」であれば、許可なしに深夜営業するのは無許可営業であり、処分対象となるので注意が必要です。
誤解②:「深夜営業なら照明は暗くても問題ない」
深夜営業=ムーディーな照明というイメージで、照度を極端に落とす店舗も見られますが、照度が低すぎると「接待性を助長している」と判断されるリスクがあります。特に風営法の許可を得ていない場合、構造や雰囲気が接待性を感じさせると、立入調査で指導・是正を受ける可能性があります。構造設備や演出は、実態と一致させることが求められます。
誤解③:「警察の立入はないでしょ?」
風俗営業に限らず、深夜酒類提供飲食店も風営法の一部規制対象であり、管轄警察署(生活安全課)による立入調査が実施されることがあります。特に開業から間もない店舗や、近隣からの苦情が出た場合には調査の対象になりやすく、違反が確認されれば営業停止や是正命令に繋がることもあるため油断は禁物です。
行政書士の視点から見る、実務上の注意点
深夜酒類提供飲食店や風俗営業の届出・許可において、現場でよくあるトラブルの多くは、事前の確認不足や「つもり営業」によって引き起こされます。
① 接待の定義に注意
「接待」とは、単に接客するだけでなく、客の隣に座る・会話を持続的に行う・お酌をする・一緒にカラオケを歌う(デュエット)といった行為を指します。これらのいずれかを満たすと風俗営業(1号営業)扱いとなり、深夜営業は不可となります。スタッフ教育や接客マニュアルの整備も不可欠です。
② 内装設計段階での相談が必須
風俗営業許可を得るには、客室の見通し・明るさ(照度)・カウンターの長さ・間仕切りの構造など、細かな物理的基準を満たす必要があります。内装工事完了後に申請が通らない例も多いため、設計段階から行政書士に相談することが極めて重要です。
③ 地域制限の確認(大阪市)
大阪市では、深夜酒類提供飲食店営業の届出が可能な用途地域は以下の通りです
- 商業地域
- 準工業地域
- 近隣商業地域
- 準住居地域(一部制限あり)
- 特定用途制限地域(条例の定めにより可)
一方、第一種・第二種低層住居専用地域などでは届出自体が不可となっています。
さらに、地域によっては大阪市独自の条例により届出後の立入調査や指導が厳しいこともあるため、事前調査と専門家への相談は必須です。
実際の摘発事例(大阪市)
大阪市では、風営法や深夜酒類提供飲食店営業に関する取り締まりが年々厳しくなっており、「つもり営業」や届出・許可の不備によって摘発される店舗も少なくありません。
以下は実際にあった代表的なケースです。
ケース①:ガールズバーが接待行為を行っていた例
表向きは「接待なしのバー」として深夜酒類提供飲食店営業の届出を提出していたが、実際には女性スタッフが隣に座り、会話やお酌、カラオケの相手をするなど明確な接待行為が確認された。結果、風俗営業無許可営業として風営法違反となり、営業停止命令と警察による厳重な指導処分が下された。
ケース②:無届で深夜営業をしていたスナック
営業許可も届出もない状態で午前0時以降も営業を続けていた店舗に対し、警察の立入調査が入り、無届営業の違反として是正命令・一時営業停止となった。
営業再開には正式な届出と構造是正が求められ、大きな損失を被った。
このように、
「接待の定義を曖昧に捉える」
「届出を出せば十分と誤解する」
「バレなければ大丈夫」
という意識で営業してしまうと、後々営業停止・風評被害・行政処分といった取り返しのつかない事態に発展する可能性があります。
まとめ:夜のお店は“線引き”が命
ナイトビジネスを始めるにあたって、風営法による「風俗営業」と「深夜酒類提供飲食店営業」の違いを正しく理解することは、営業の成否を左右する重要なポイントです。
どちらの制度に該当するかは、単に店の名前やコンセプトで決まるのではなく、「接待行為の有無」と「営業時間」が最大の判断基準になります。
- 接待がある → 風俗営業許可が必要(原則24時まで)
- 接待がない → 深夜酒類提供の届出でOK(深夜営業も可)
接待行為が1つでも認められれば、届出ではなく許可が必要となり、これを誤ると無許可営業として営業停止や行政処分のリスクに直結します。
また、深夜酒類営業であっても地域制限や店舗構造、照度など、実は見落とされがちな規制が多数存在します。
さらに、最近の大阪市をはじめとする都市部では、警察による立入調査や摘発事例も増加傾向にあり、「知らなかった」では済まされない時代になっています。