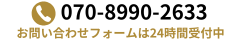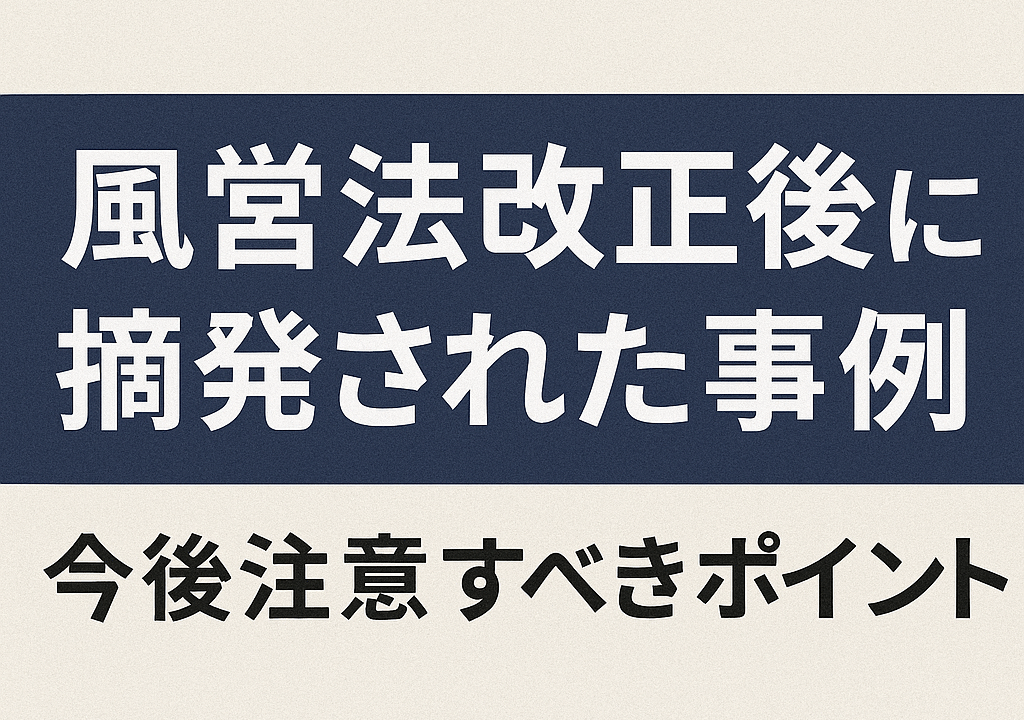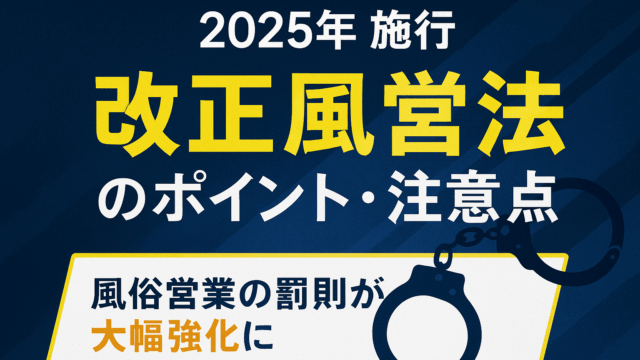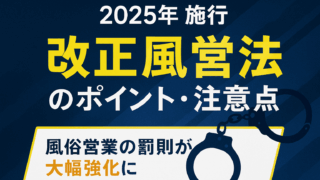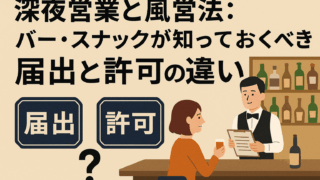はじめに
2025年6月28日、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)が大きく改正され、全国の飲食業界・ナイトビジネスに激震が走りました。
今回の改正では、無許可営業に対する罰則の大幅強化や、悪質なホストクラブ営業の摘発強化が盛り込まれ、「実態重視・即時摘発」の運用方針が明確になりました。
施行初日から、ガールズバー・ホストクラブ・マッサージ店など、全国各地で実際の摘発事例が相次ぎ、従来であれば「グレー」とされていた営業形態にも厳しい目が向けられています。
制度を正しく理解し、健全な経営体制を整えることが、今後の店舗運営の生命線です。
改正風営法とは?
2025年6月28日に施行された改正風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では、無許可営業の取締り強化と、悪質なホストクラブ営業への明確な対応が柱となっています。
まず、無許可営業に対する罰則が大幅に引き上げられ、これまでの罰金刑(個人100万円以下・法人200万円以下)から、個人では最大1,000万円、法人では最大3億円までの罰金が科される可能性が生じました。
これは実質的に「一発営業停止・経営破綻」を意味し、これまで“グレー”とされてきた接待行為にも厳格な運用がなされます。
さらに、ホストクラブを中心とする“恋愛感情を利用した営業”に対して、売掛金の過大請求、強引な同伴営業、性的サービスの強要などが「風営法違反」として摘発対象に明記されました。単なる風俗営業の枠を超えた精神的・経済的搾取への規制強化ともいえます。
参考URL:
https://www.asahi.com/articles/ASR6X7HZLR6XUTIL00F.html
2025年6月末〜現在の摘発事例
(1) 東京都・新宿・歌舞伎町ガールズバー 摘発
2025年6月28日、新法施行初日に東京都・新宿歌舞伎町のガールズバー経営者が、無許可で女性従業員に接待行為(カウンター越しに酒を注ぎ、会話するなど)をさせた疑いで現行犯逮捕されました。
行政指導を経ても改善されず、鏡を使って下着を見せるなど悪質性が高いと判断されたケースで、改正風営法の全国初適用事例です。この摘発は、「指導では改善されない営業に対し即時摘発する」という警察の姿勢を如実に示すものとなりました。
参考URL:asahi.com+13
(2) 東京都・町田市など8店舗一斉摘発
同警視庁は6月30日までに、歌舞伎町を含む都内7地区でガールズバー8店舗を一斉摘発。従業員に接待行為をさせ、許可を得ずに営業していた経営者約12人が逮捕または書類送検されました。多くの店舗は過去に行政指導を受けていたにもかかわらず改善がなく、罰金や許可取得を怠った点が強く追及されています。
参考URL:newsdig.tbs.co.jp
(3) 福岡・中洲の“ホストクラブ風営業”摘発
6月30日、福岡県警は、5月25日から中洲のバーを装って女性客に接待行為を行ったとして、ホストクラブ経営者ら4人を逮捕。シャンパン1本50万円の高額営業で、無許可営業の典型例と見なされました。これは改正法施行後、全国初のホストクラブ摘発事例となり、悪質性が高い営業形態への強い監視を示唆しています。
参考URL:asahi.com+14
(4) 愛知・豊田市でマッサージ店装いの性風俗サービス摘発
6月29日、愛知県豊田市では、営業禁止区域内にてマッサージ店と偽り性的サービスを提供していたとして、中国籍従業員(30代女性)が現行犯逮捕されました。同事件は、改正法による性風俗サービス摘発として県内初であり、「営業禁止区域」「外国人従業者」の観点からも法遵守の重要性が浮き彫りになりました。
参考URL:news.tv-asahi.co.jp
行政書士の視点:摘発背景と解説
改正風営法施行後の各摘発事例を検討すると、警察の運用方針が「実態重視」「即時対応」に転換されたことが明白です。
形式上の名目ではなく、営業実態に即して違反か否かが判断されており、許可未取得のまま営業を継続することのリスクが極めて高まっています。
“接待行為”を伴う営業は許可必須
風営法における「接待」とは、客の身辺に付き従い、歓楽的雰囲気を助長する行為を広く含みます。ガールズバーやホストクラブに限らず、従業員がカウンター越しで会話やゲームに同席する行為も「接待」とされ、許可を受けずに行えば無許可営業として処罰対象になります。
罰則強化による即時摘発の可能性大
従来の上限刑(個人100万円、法人200万円)では違法営業の抑止力が弱く、警告止まりのケースも多く見られました。改正後は最大3億円という罰則が導入され、警察側も警告ではなく初手での逮捕・摘発に踏み切る傾向が強まっています。
悪質ホストには恋愛感情悪用条項が適用される
恋愛感情を利用した売掛制度や、精神的・肉体的支配のもとでの過剰請求・性的強要などは、改正法で明確に規制対象となりました。ホストクラブに対する従来の「業態的曖昧さ」は排除され、風営法・刑法両面からの摘発が可能となっています。
今後の店舗経営者が注意すべき重要ポイント
改正風営法の施行により、店舗経営者は従来以上に制度理解と運営管理の厳格化が求められます。以下の観点から営業体制を見直し、法令遵守とリスク回避を徹底する必要があります。
(A) 許可取得が必要な営業形態の再確認
カウンター越しでの会話、接客、ドリンク提供、ゲームの同席など、いわゆる「接待行為」が含まれる営業は、風俗営業1号(接待飲食等営業)に該当し、風俗営業許可の取得が必須となります。営業内容によっては、2号(低照度)や3号(区画構造)に該当する場合もあり、事前の営業分類の精査が不可欠です。無許可のまま接待を行えば、刑事責任と営業停止のリスクを負うことになります。
(B) 営業場所と地域規制のチェック
店舗の所在地が都市計画法における「用途地域」に適合していない場合や、保全対象施設(学校、病院、図書館等)から一定距離以内にある場合、許可そのものが取得できない可能性があります。出店前には市区町村の都市計画課・建築指導課などで用途地域の調査を行い、風営法上の営業可能エリアかどうかを確認することが不可欠です。
(C) 構造設備・内部管理の整備
営業許可には、物理的構造の基準も厳格に定められています。例えば、客室の照度が5ルクスを超えていること、個室・仕切りのない見通しの良い構造であること、従業者名簿、年齢確認記録の整備などが求められます。これらの項目が不備である場合、許可の更新・維持にも支障を来します。
(D) 看板・広告内容の規制強化
店舗の広告・看板に関しても、風営法・屋外広告物条例・景観条例などの複合的な規制が適用されます。特にホストクラブにおいては、「○億円プレイヤー」「伝説のホスト」など、虚偽・誇大表示とみなされる文言は規制対象となっており、行政から指導・改善命令を受ける事例が増加しています。
(E) スタッフ教育の徹底
従業員が法令を理解していなければ、意図せずに無許可営業に該当する行為を行うリスクがあります。「接待はするな」だけでは不十分であり、風営法の趣旨、接待の定義、刑事責任の有無などを理解させる研修の定期実施が望まれます。管理者に対しては、特に実務的な教育・マニュアル整備が求められます。
(F) 外国人雇用・個別対応
外国人従業員の採用に際しては、就労ビザの種類・在留資格・風営法との整合性の確認が必要です。特に接待行為に従事させる場合には、原則として在留資格が付与されないため、違法就労助長罪などにも発展しかねません。採用前に行政書士等による個別の在留資格確認と届出義務を徹底すべきです。
行政書士からのアドバイス
事前申請の徹底
営業形態に「接待行為」が含まれるか、店舗構造が基準を満たしているか、所在地が営業可能な用途地域かなどを慎重に確認し、警察署との事前協議も含めて、適切な風俗営業許可申請を行うことが第一です。特に構造確認と住民対策は行政書士の同行を推奨します。
抜け漏れ防止のためのチェックリスト作成
照度、個室構造、防犯カメラ、従業者名簿、年齢制限掲示、屋外広告の文言など、実地確認すべき項目は多岐にわたります。これらを網羅的に点検するため、行政書士監修のチェックリストを用いた運用が不可欠です。
教育・内部規程の整備
違反を未然に防ぐには、従業員への教育体制が要です。接待の定義や広告規制を明記した社内マニュアルを整備し、定期的な研修や監査を実施することで、内部統制を強化しましょう。
悪質営業への警戒
ホストクラブなどで見られる恋愛感情の悪用やツケ制度による過大請求は、改正風営法における新たな摘発対象です。風営法だけでなく、消費者保護や刑法上のリスクにも備えた多角的なガバナンスが求められます。
おわりに
改正風営法の施行により、無許可営業や悪質な営業形態に対する摘発が全国で相次ぎ、取り締まりはこれまでにない厳格さを見せています。
従来の“黙認”や“グレーゾーン”は通用せず、実態に基づいた厳しい判断が下される時代に入りました。
行政書士としては、営業許可の取得だけでなく、構造・照度・広告・従業員管理などの法令遵守体制を整えることが、安全な店舗運営の鍵と考えます。