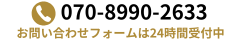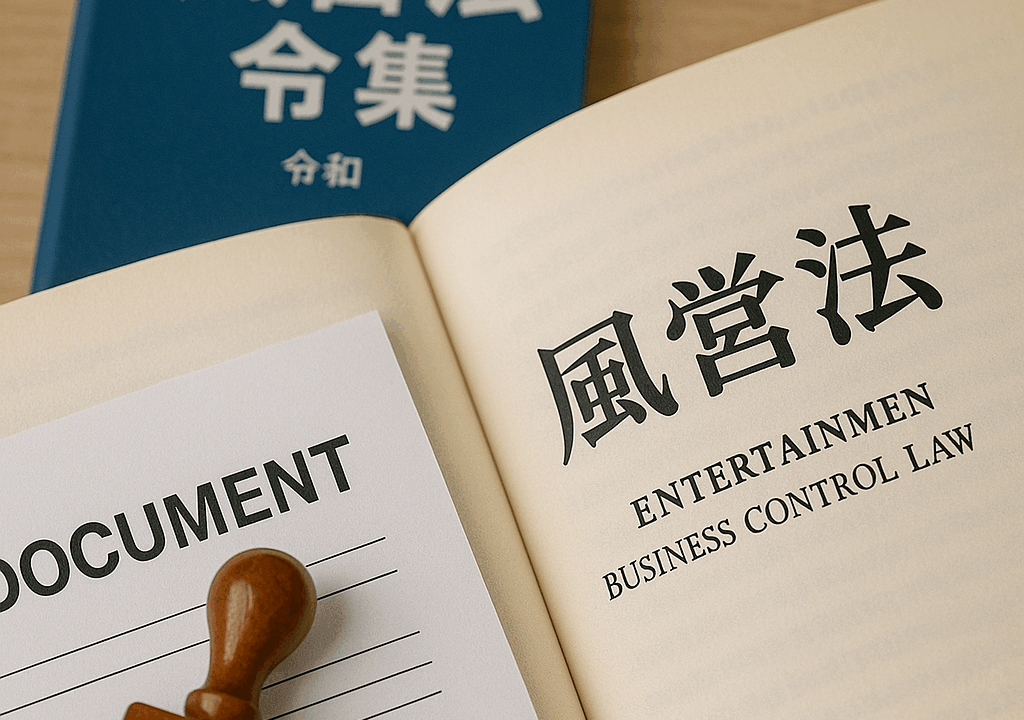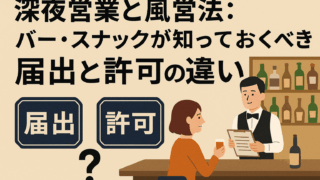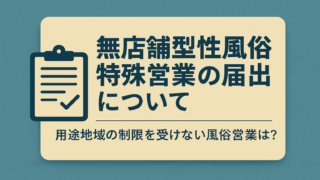はじめに
風俗営業の許可取得において、建物の「構造要件」を満たしているかどうかは、申請の可否を大きく左右する重要なポイントです。
中でも「客室の見通しを妨げる構造」については、警察署の実地調査でも最も厳しくチェックされる項目の一つであり、不備があると許可が下りない、あるいは改善命令の対象となる可能性があります。
構造要件とは? 風営法の根拠規定
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、社会の風紀・善良な風俗の保持を目的としており、一定の業種に対して営業許可を課しています。
この構造要件は風営法施行規則第4条に詳細が定められており、具体的には以下の項目が求められます。
- 客室の床面積(1室9.5㎡以上)
- 照明の明るさ(照度10ルクス以上)
- 客室の見通しを妨げる設備がないこと
- 遮音構造、外部からの視認防止
- 客室以外の場所(通路・控室・倉庫等)との区分け
これらの基準を満たしていない場合、営業許可が下りません。
「見通し制限」とは? なぜ重要なのか
風営法では、営業所の客室において「見通しを妨げる設備・構造」があることを原則として禁止しています。
これは、営業の実態を外部から適切に把握できるようにすることで、違法行為の発生を防止するという目的があります。
たとえば、密室化された空間での過剰な接待、売春行為、暴力団関係者による不適切な利用などが起こりやすくなるため、そのようなリスクを排除するために「見通し制限」が設けられているのです。
ここでいう「見通し」とは、店舗内の客席全体を1人の視点から概ね見渡せる状態を指します。
つまり、死角がないことが求められます。客席の奥まったボックス席、柱や間仕切り、ラック、ついたて、棚などで客席の一部が遮られてしまう場合、それが「見通しを妨げる構造」とみなされることがあります。
特に、カウンターの裏側や壁の陰など、スタッフや監視者の目が届きにくい場所がある場合、許可が下りない、あるいは改善指導の対象になることもあります。
そのため、店舗設計の段階で見通しの確保を最優先し、間取りや家具配置には十分な注意が必要です。
見通しを妨げるとされる主な構造や設備
風営法において「見通しを妨げる」と判断される具体例は以下のとおりです。
(1)間仕切り・パーテーション
最も典型的な例です。
腰高や天井までの間仕切りはもちろん、半透明のアクリル板や装飾性の高いスクリーンであっても、「客室の見通しを妨げる」と判断されることがあります。
特に着脱式のついたて等は「営業開始後に見通しを遮るおそれがある」として厳しく指導されるケースが増えています。
(2)棚・ラック・テレビ台
あまり知られていませんが、以下のような家具類も違反対象になる可能性があります。
- 高さのあるラック
- 壁付けの飾り棚
- パーテーション代わりに使われているTVボード
特に高さが90cmを超えるものは、ボックス席やカウンターの視界を遮ると判断されやすくなります。
壁際に設置されている場合でも、店舗全体の構造次第では見通しの妨げとされるため、設置場所や高さに配慮が必要です。
(3)カーテン・のれん・布地
軽量であっても「客室と客室を区切る意図」で設置されているものはNGです。
装飾目的のレースカーテンや布も、「構造上不要」と判断されれば指摘される恐れがあります。
「構造上必要」とされる例外とは?
風営法における構造基準は厳格に定められていますが、一定の柔軟性も持たせられており、設備や構造物が「建物の構造上必要である」と認められる場合には、たとえ見通しを妨げていても許可が下りるケースがあります。
これは風営法施行規則において例外的に認められているもので、単なる装飾や後付けの設備とは明確に区別されます。
たとえば以下のようなものが該当します。
- 店舗の柱や梁(はり)など、建物の強度維持に必要な構造物
- 建築時に一体化して設置された腰壁
- 空調や給排気設備のカバーやダクトボックス
これらは、設計段階から建築に組み込まれており、後から取り外すことが困難なため、「構造上必要」とみなされることがあります。
ただし、その判断は一律ではなく、最終的には各地域の管轄警察署・生活安全課が個別に判断します。
したがって、営業所の図面において見通しを妨げるような構造がある場合は、申請前に必ず事前相談を行い、図面や写真を提出して確認を受けることが極めて重要です。
事前確認を怠ると、申請却下や是正指導の対象となるおそれがあります。
よくあるトラブル・NG事例
風営法の構造要件、とくに「見通し制限」は判断基準が厳しく、ちょっとした認識のズレがトラブルや摘発につながることがあります。以下のようなケースは特に注意が必要です。
- 申請時はついたて等を外していたが、営業開始後に設置した → 指導・摘発対象
- カウンターと客席の間に高さ1mの棚を置いていた → 見通し制限違反
- 構造上必要と誤解し、壁を設置 → 図面不備で申請却下
- 控室と客室を明確に区分けしていなかった → 区分構造要件違反
- 客室の一部を物置スペースとしてパーテーションで仕切った → 見通しを妨げる設備と判断
- 店舗奥のボックス席にカーテンを設置 → 死角となり不許可
- テレビやポスターで一部の座席の見通しが遮られていた → 是正指導
これらのトラブルは、制度の誤解や軽視、あるいは申請書類と現地の構造が一致していないことに起因しています。
たとえば、営業所の内装工事後に家具を追加したり、インテリアを変更した結果、当初は問題なかった構造が「見通しを妨げる」と判断されることもあります。
申請時だけでなく、営業後のレイアウト変更にも細心の注意が必要です。
また、申請前に専門家(行政書士など)に図面チェックや現地確認を依頼することが、許可取得とトラブル回避の大きな鍵となります。
行政書士ができるサポート
風営法の許可申請において、構造要件の判断は非常に専門性が高く、一般の方が独力で図面を作成・調整するのは困難です。
弊所はは以下のような支援が可能です。
- 図面作成(求積図・構造設備図など)
- 現地調査に基づく改善点の指摘
- 警察署との事前相談の同行
- 構造要件クリアのための改装アドバイス
- 見通しに関する誓約書の作成
特に、構造上不要な設備を「営業では使用しない」と誓約する文書(例:カウンター部分を接待に使用しない等)は、警察への説得材料として効果的です。
まとめ:申請前の構造チェックが許可取得の鍵
風営法の構造要件、とりわけ「見通し制限」は許可申請において最重要ポイントの一つです。営業者の善意や営業実態がどうであっても、「物理的な構造」で判断されるのが原則であり、些細な構造物でも不許可の原因となります。
許可をスムーズに取得するためには、営業開始前の段階で専門家による構造チェックを受けることが極めて重要です。
特に新規で物件を取得・改装される場合は、内装工事の前に風営法の基準を確認し、それに基づいた図面設計を行うことで、無駄な手戻りやリスクを回避できます。